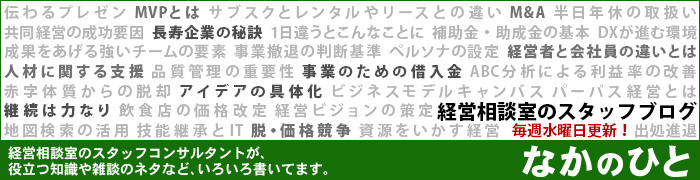
※土日祝除く
ボジョレー・ヌーボーの限定マーケティング
- ボジョレー・ヌーボーの限定戦略
- ボジョレー・ヌーボーを支える2つの価値
- 市場変化への対応
ジョレー・ヌーボーの限定戦略
来週の11月20日はボジョレー・ヌーボー解禁日ですね。個人的にはワインよりも新酒のキャッチコピーを楽しみにしております。

欲しくなる理由をつくりましょう。
さて、今回はボジョレー・ヌーボー解禁日にも関係のある、限定マーケティングについてまとめました。一見、お祭りのイベントですがマーケティングに裏打ちされた人気の理由や、「誰が一番乗りで飲むか」を競うイベント性など、昨今の時流に合わせた取り組みについてみていきたいと思います。
ボジョレー・ヌーボーを支える2つの価値
ボジョレー・ヌーボーを支えるマーケティング手法は①「ニッチ戦略」としての限定性、②「非日常体験」としてのイベント要素があげられます。
①「ニッチ戦略」としての限定性
ボジョレー・ヌーボーは、解禁日(毎年11月の第3木曜日)以前には飲めません。この「たった一日」の解禁日が、商品の限定価値になっているのはいうまでもありません。ワインの銘柄や価格に関わらず、全てのボジョレーに「この日限りの消費期限」のような限定感です。「今買わなければ」「この機会を逃したら損だ」という購買動機(以前、紹介したFOMO:取り残される不安)のきっかけになります。
②非日常体験
その時だけの新酒であることに加えて「解禁」というキーワードで限定されていることで非日常性が高まります。さらに日付を設定していることで、「解禁日まであと3日」など非日常的なカウントダウンイベントなどを企画しやすくなります。全世界で解禁日が統一され共有できることがボジョレー・ヌーボーならでは価値といえます。こうした解禁日を用いたマーケティングは推し活マーケティングでも用いられ“情報解禁日”、“公開記念カウントダウン”といったイベントが行われています
ちなみに、日本でボジョレー・ヌーボーが流行ったのは、時差の関係で、世界でもっとも早く解禁されるといった要素も大きいようです。また「初物七十五日」(※1)といって日本は古くから縁起物として好まれる文化的な背景も関係があるようです。
こうした限定価値は時間が経過すると旬が過ぎてしまうこともあるので、不良在庫などへの注意が必要です。ボジョレー・ヌーボーの場合、フランスのワイン法によりボジョレー・ヌーボーは毎年12月10日までには出荷を終えるように定めされています。
市場変化への対応
昭和や平成の時代では、ボジョレー・ヌーボーは一番乗りを競い合うようなイベントでしたが、令和では、インターネットを活用し自分の気に入ったものを買うという行動が主流のようです。これには世界的なインフレや円安の影響によりワインも高額になったことに加え、飲み会や外食が減り宅飲みにシフトしていること、SNSが普及したことなど外部環境の変化が大いに影響しているものと考えられます。
こういった変化は、キャッチコピーにも反映されています。ちなみに日本の飲料メーカーが発表した2024年のキャッチコピーは「果実がダンス! ジュワっとジューシーな味わい」です。平成で流行った大げさな表現から、生産地での評価に沿った具体的な表現方法に変わっています。昔の表現、しばらくは味を具体的にイメージできるようなものが続きそうです。
限定価値の見せ方も大きな外部環境の流れに沿って、時流に合わせた対応が求められますね。
経営相談室 スタッフコンサルタント 大西が担当しました。
(※1)初物七十五日
「その季節に初めて出回る『初物』を食べると、寿命が75日延びる」と言われ縁起がよいものとされてきました。
▼大西 森(おおにし しげる)へのご相談(面談)
(2025年11月12日公開)
この記事に関連する大阪産業創造館のコンテンツ















