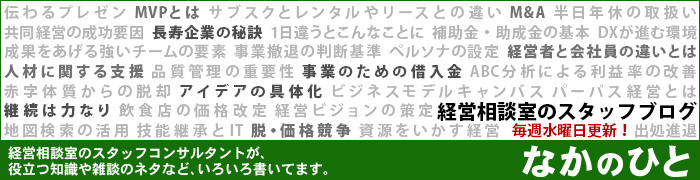
※土日祝除く
高年齢雇用継続給付の改正から考える定年再雇用
- 高年齢雇用継続給付の給付率引き下げ
- 『定年再雇用=待遇引き下げ』の是非
- 給与・手当の目的を整理しよう
高年齢雇用継続給付の給付率引き下げ
みなさん、こんにちは。経営相談室の高松です。
ついこの前、2025年が始まった!と思っていたのですが、気づけはもう3月になっていました。4月からの新年度を迎えるにあたり、人事労務制度の改正に関するチェックはお済でしょうか?2025年度も、多くの変更があります。
特に、事業者側にとっても労働者側にとっても影響が大きいと思われるのが、「高年齢雇用継続給付」の給付率引き下げです。

令和の60歳はまだまだ働き盛り!
厚生労働省:「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00043.html
「高年齢雇用継続給付」とは、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給される給付金です。これまでは、各月に支払われた賃金の15%を限度として支給されていましたが、2025年4月1日以降は、各月に支払われた賃金の10%が限度となります。
『定年再雇用=待遇引き下げ』の是非
深刻な人手不足の折、60~65歳の人材は貴重な労働力のはずなのに、給付率が引き下げられるなんてけしからん!と思われる方もいらっしゃるかもしれません。ですが、給付率が下がることの是非の前に、そもそもの問題点は、「定年再雇用になったときに給与が引き下げられる運用が広く行われている」ということではないでしょうか。
2021年4月に「高年齢者雇用安定法」の改正が施行され、事業主は従業員に対して、65歳まで雇用を確保する義務が定められています。この雇用確保義務は、必ずしも正社員である必要はないため、多くの会社では「60歳で定年退職後、再雇用で嘱託社員になって65歳まで契約」といった運用が取られています。そして、契約形態の変更と給与の引き下げがセットで行われてきた、という現状があります。
契約形態が変更になっても、「同一労働同一賃金」の観点からすると、仕事内容が同一であれば、同等の賃金を支払わなければなりません。つまり、給与を引き下げるということは、給与に見合った軽微な仕事しか任せられない、ということにつながります。まだまだしっかり働きたい!これまで培った経験やスキルを活かしたい!と考えている従業員であれば、会社で働き続けるモチベーションが下がってしまいそうです。
給与・手当の目的を整理しよう
定年再雇用をきっかけとする給与などの待遇引き下げをめぐって、裁判例も増えてきました。裁判で争われるケースの多くは、「正社員で働いていた時の仕事内容と定年再雇用後の仕事内容が同じなのに、給与などの待遇が引き下げられたのはおかしい」というものです。判例では、給与の引き下げが即違法、というわけではなく、「給与の性質や目的を踏まえて合理性を評価すべき」という枠組みが示されています。正社員と正社員以外で差を設けるのであれば、合理的な理由が必要、ということです。仕事の内容が異なる、責任の範囲が異なる、転居を伴う異動がある…など、待遇の差を生じる理由があるか?を確認して、理由がなければ是正を図る、といった取り組みが求められます。
給与設計は経営の根幹に当たる課題です。経営相談室の専門家相談も活用して、時代にフィットした給与を設計しましょう。
経営相談室 スタッフコンサルタント 高松が担当しました。
▼高松 留美(たかまつ るみ)へのご相談(面談)
(2025年3月5日公開)
この記事に関連する大阪産業創造館のコンテンツ















