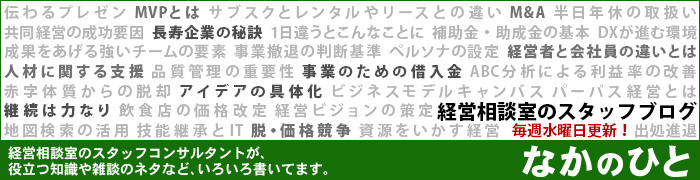
※土日祝除く
話題のアニメに学ぶマーケティング戦略
- 人気アニメはいかにして作られたか
- SNS時代の市場調査とSTP分析
- 偶然の中の必然
人気アニメはいかにして作られたか
連載漫画や小説からの毎年アニメ作品が生まれファンを楽しませてくれています。多くの作品が発表される中で、注目される話題作が必ずあります。今回は、2025年冬シーズンで話題となった「悪役令嬢転生おじさん」を取り上げ、マーケティングプロセスを解説します。

マーケットの熱量を図る
さて「悪役令嬢転生おじさん」はいわゆる“転生もの”です。主人公は私と同世代の52歳のおじさんです。ひょんなことから、乙女ゲームに悪役令嬢として転生することでストーリーが展開していきます。
作者の上山道郎氏によると、直近の連載が打ち切りになったことに危機感を覚え、近年のトレンドを学ぶために「異世界転生もの」を読み漁ったそうです。その中でも気に入った「悪役令嬢もの」で自分が読んでみたいと思いついたプロトタイプを同人漫画としてSNSで発表しました。この結果、約16万いいねという爆発的な反響があり、商業化につながったということです。
SNS時代の市場調査とSTP分析
作品が生まれた背景は、一見するとサクセスストーリーそのものですが、ここにはマーケティングの教科書に出てくるSTPのフレームワークがしっかり反映されています。
◆S(セグメンテーション):市場の細分化
最近の小説や漫画のトレンドである「異世界もの」からさらに「悪役令嬢もの」を見ているセグメントへ細分化しています。一般的なセグメントでは、年齢層や性別などでセグメントされることもありますが、ファンがどこに注目しているかトレンドを確認して「悪役令嬢もの」という“作品ジャンル”で細分化しています。
◆T(ターゲティング):狙う市場を決定
作者自身の興味があったジャンルとしている点やSNSで同人漫画として発表している点などから、作者自身と同世代(50代前後)のアニメファンがコアなターゲットであると推察できます。
◆P(ポジショニング):差別化・独自性
本作最大の特徴は、「おじさんが悪役令嬢に転生する」という異色の設定です。
「異世界転生もの」「悪役令嬢もの」という型を踏まえつつ、「おじさん」という意外性のある要素を加え、他作品との差別化に成功しました。
また、定番の基本設定は崩さず、独自性と安心感のバランスを取っている点も秀逸です。
偶然の中の必然
この作品をひらめいたのは漫画家ならではの独創性が大いにあると思いますが、流行を踏まえつつSNSでの反響をみて、マーケットの熱量を図るプロセスはSNS時代ならではのものです。
また意図していたか不明ですが、STPのフレームワークどおり市場を深く分析し、独自性と強みが生かせるポジショニングを確立し、市場の反応をリアクションから検証しています。
さらにアニメの放送直後は常にトレンドキーワードをにぎわせていました。ターゲットである“アニメで育った世代”に刺さる他作品のオマージュが散りばめられ、インターネット上でファン同士が「あの作品からだよね。」と盛り上がるポイントを提供していました。その結果、放送を毎週楽しみにしているファンを中心にSNS上で盛り上がり、口コミで幅広い世代に広がる好循環が生まれました。
ヒットの要因は、作品そのものの魅力、有名なアニメーション制作会社、声優など他にも多くあります。マーケティング視点で見ると「悪役令嬢転生おじさん」は市場の期待に応え、情報発信と市場との対話を大切にした戦略 があります。作品の独自性に加え、感想を共有できるポイントを織り込むなど、SNS時代のマーケティングにおいて非常に参考になる事例 です。
商品やサービスを企画する際も、“市場の細分化”、“明確なターゲティング”、“独自性のあるポジショニング”、“SNSを活用した市場の反応確認”を意識することで、偶然ではない必然のヒットを生み出せるかもしれません。
経営相談室 スタッフコンサルタント 大西が担当しました。
▼大西 森(おおにし しげる)へのご相談(面談)
(2025年4月23日公開)
この記事に関連する大阪産業創造館のコンテンツ















