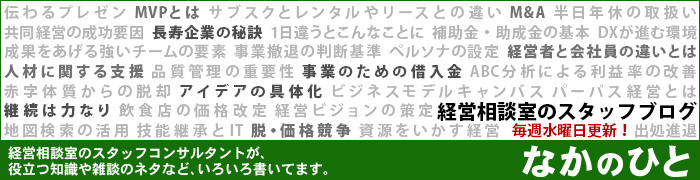
※土日祝除く
物価高騰時の購買行動はどうかわるか?
- 物価高騰時に求められる工夫
- 消費者の購買行動はどうかわる?
- 変化を前提とした柔軟な対応
物価高騰時に求められる工夫
某ドーナツチェーン店では、この時期になるとショコラティエとコラボレーションしたメニューが登場します。従来品よりも強気の価格設定ですが、店舗の前には列ができる人気商品になっています。背景には「話題性の高い魅力的な商品なら並んでも買いたい」といった顧客ニーズも伺えます。

変化に向けて柔軟な対応を考えましょう
これまでのコスト上昇局面では、いかに価格転嫁するかが中心テーマですが、この事例のように高付加価値化により顧客ニーズを捉えようとする動きも見られます。
高付加価値化というと難しいですが、「高くても買ってもらえる理由を考えること」なので、「機能的な価値を追加する」「ここでしか買えないという希少性を高める」「ストーリーをつける」「サービスを強化する」といった工夫です。
低価格で気軽にたくさんドーナツを買えたころも懐かしいですが、環境変化は今後も続きそうです。
今回は消費者行動の変化を捉える経済学のモデルについてご紹介します。
消費者の購買行動はどうかわる?
物価高騰が継続する局面では、実質所得が低下し、消費者は価格に対してよりシビアな態度をとります。こうした購買行動の変化に合わせて企業側も対策が必要となります。
①価格の弾力性を踏まえた対策、②価格上昇を受け入れやすい付加価値の提供、③情報の透明性を高めることといったものです。
①「価格の弾力性」を踏まえた対策
「価格の弾力性」とは、価格上昇に対し消費がどれだけ変化するかの指標です。嗜好性の高い商品(=価格の弾力性が高い)は、売れにくくなり、生活必需品など(=価格の弾力性が低い)は値段が上がっても一定の消費が維持されます。
“価格の弾力性が高い商品”については、付加価値の提供(次項参照)が求められます。逆に“価格の弾力性が低い商品”は、より安い商品へ消費が置き換わることがあるので、まとめ買いや機能を絞り込んだ低価格商品の提供などにより、他社製品への切り替え防止対策が求められます。
②受け入れられやすい付加価値の提供
「この価格でも買いたいと思える要素」を強化し、高くても買ってもらえる理由を検討します。例えば、「長持ちする」「より便利」「環境に優しい」など価格以外の魅力を明確にし、単純な値上げではなく、納得できる状態を作ることが求められます。
③情報の透明性を高める
価格上昇時、消費者は懐疑的になり、“不当な値上げ”と受け取れられやすくなります。そのため、価格転嫁の背景を適切に伝えることが、購買意欲を維持するカギとなります。
変化を前提とした柔軟な対応
今回は、“価格の弾力性”を踏まえた対応方法を紹介しました。こうしたモデルでは大きな流れは把握できるものの、会社によって対応方法は一様ではありません。ドーナツ店のケースでは、話題性のある商品を投入しつつ、価格改定の説明はしっかり行うなどきめ細かい対策が取られています。それぞれの経営環境に応じて、事例などを参考に顧客の行動を正しく捉え柔軟に対応していく中で、手掛かりが見つけられることもあります。
経営相談室 スタッフコンサルタント 大西が担当しました。
▼大西 森(おおにし しげる)へのご相談(面談)
(2025年2月26日公開)
この記事に関連する大阪産業創造館のコンテンツ















