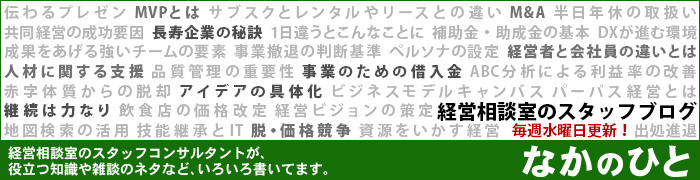
※土日祝除く
実はいろいろある産休・育休にまつわるお金の支援
- 出産・育児にはお金がかかる
- 産前産後の経済的支援
- 育休中の経済的支援
出産・育児にはお金がかかる
みなさん、こんにちは。経営相談室の高松です。
さて、今回も、産休・育休に関する話を取り上げます。
ここ数年、産休・育休制度が充実してきた背景には、おそらく少子化への対応という側面があると思います。厚生労働省によれば、令和6年の出生数は68万6061人(前年は72万7288人)(※1)と、大きく減少しました。

充実している産休・育休支援制度
少子化の要因の一つとして挙げられるのは「経済的な負担の大きさ」。こども家庭庁の【令和4年度 少子化の状況及び少子化への対処施策の概況(※2)】によれば、理想こども数を持たない理由として「子育てや教育にお金がかかりすぎるから」が多数に上るという結果が出ていました。
そこで、今回は出産・育児に関連する経済的な支援制度(社会保険関連)を取り上げます。
産前産後の経済的支援
厚生労働省の調査(※3)によれば、正常分娩での出産費用(出産時に本人が負担する額)は、おおむね50万円程度となっています。
この約50万円の費用を賄ってくれるのが、「出産育児一時金」です。健康保険・国民健康保険など公的医療保険から、出産1人につき原則50万円が支給されます。
「直接支払制度」を利用できれば、本人が病院の窓口で支払う金額は、費用の総額から出産育児一時金の支給額を差し引いた残りの額で済みます。いったん立て替えて還付を受ける場合と比べて、まとまったお金を用意しなくてもいいという点で、非常に大きなメリットといえます。
また、働いている本人が出産をする場合、産前産後休業を取得します。産前産後休業期間中を有給とするか無給とするかについては、法律上の規定はありません。そのため、多くの会社が無給としています。
この間の生活資金を賄う制度として、「出産手当金」があります。こちらは健康保険(協会けんぽなど)の被保険者が対象で、毎月の給与のおおむね3分の2にあたる金額が支給されます(ただし、国民健康保険の被保険者は対象外となります)。
さらに、給付ではありませんが、産前産後休業期間中は社会保険料が免除されます。従業員だけでなく、会社負担分も免除される上、免除期間中も被保険者資格に変更はなく、将来、年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われるというのは大きなメリットではないでしょうか。
育休中の経済的支援
社会保険料については、産前産後休業と同様、育児休業でも免除制度があります。社会保険料は本人負担・会社負担を合わせると、総支給額の3割相当の額ですので、これらが免除の上、年金額の計算上は保険料を納付している期間として扱われる、というのは非常にありがたい制度と言えます。
給付については、「育児休業等給付」(いわゆる育休手当)があります。こちらは雇用保険から受ける給付です。給付の時期や対象者によって細かく制度名が分かれているため、「育児休業『等』給付」という総称がつけられています。支給額は、休業開始時の賃金の80%(支給上限額あり)となっています。出産育児一時金や出産手当金と異なり、雇用保険からの給付のため、対象者は雇用保険の被保険者のみです。給与と全く同じ水準の給付とはいきませんが、社会保険料の負担がないことを思えば、手取りは大きく変わらないとも言えます。
今回は、出産・育児に関する社会保険の支援制度を中心にご紹介しました。給付・免除に関する主体が健康保険、年金、雇用保険に分かれているため、全体像が把握しにくいかと思います。どこに問い合わせればいいのかよくわからない、という場合は、経営相談室の専門家相談をご利用ください。
経営相談室 スタッフコンサルタント 高松が担当しました。
※1 出典:「令和6年(2024)人口動態統計月報年計(概数)の概況」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai24/index.html
※2 出典:「令和4年度 少子化の状況及び少子化への対処施策の概況(報告書)」(こども家庭庁)
https://www.cfa.go.jp/resources/white-paper/past
※3 出典:「第186回社会保障審議会医療保険部会(ペーパーレス) 資料(【資料4】出産費用の状況等について)」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45733.html
▼高松 留美(たかまつ るみ)へのご相談(面談)
(2025年8月6日公開)
この記事に関連する大阪産業創造館のコンテンツ















