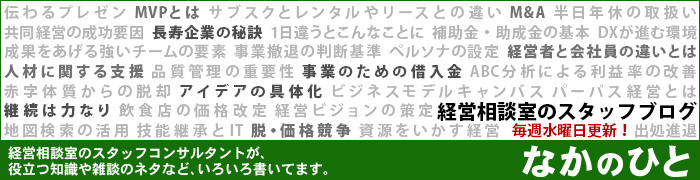
※土日祝除く
「5つの適正」で考えるファッションのサステナブル
- ファッション業界のサステナブルシフト
- ファッションをサステナブルにするために
- 「5つの適正」でサステナブルシフトを考える
ファッション業界のサステナブルシフト
イギリスの「Coldplay」は、環境活動でも有名なアーティストです。2024年には再生プラスチックCDを使用したアルバムをリリースし、ツアーでは、再生可能エネルギーを活用しています。地球を守る行動という新しい価値観を共有しながら、ファンと一緒に環境対策に取り組んでいます。

「5つの適正」でサステナブルを考えよう
音楽の分野だけでなく、ファッション業界でもサステナブルが進んでいます。フランスの「衣類廃棄禁止令」やニューヨーク州の「ファッション・サステナビリティ&ソーシャルアカウンタビリティ法案」など、法整備化が進んでいることもあり、企業は衣服を「長く使う」という価値観への対応が求められています。
環境省の調査によると、服1着あたりの製造には約25.5kgのCO2が排出され、廃棄される洋服の68%が焼却や埋め立て処理されているとあります。(※1)このように環境負荷が高いことも憂慮され、差し迫った課題となっている持続可能なファッションへの転換(サステナブルシフト)には、生活者の行動様式の変更も求められるため、なかなか進みにくいのが現状です。
ファッションをサステナブルにするために
ファッションをサステナブルにするには、生活者と企業に以下のようなアプローチが求められます。
<生活者>
「服を長く大切に着ること」
「リユースも活用してファッションを楽しむこと」
「先のことを考えて買うこと」
「作られ方を確認すること」
「服を資源として再活用すること」
<企業>
「長期間着られる服の企画」
「リペアやリユースの推進」
「購入時の慎重な選択」
「トレーサビリティの確保」
「服の再資源化」
昭和の時代にあった“お下がり”や“お直し”など、ものを大切にする習慣へ、逆戻りする印象がありますが、新たに取り組んで事業化に成功している企業も多くあります。
例えば、サルト株式会社は、オーダーメイド品に10年間の保証をつけ、「受け継いで着る」という価値を提案し販売しています。(※2)また、株式会社ユナイテッドアローズの「REプロジェクト」では、修理された服や雑貨を販売することで、年間5,000件以上のリペアを対応し顧客との新しい接点を生み出しました。(※3)
2つの事例は、環境変化と顧客ニーズを上手く汲み取って、顧客満足度を高めつつ環境負荷を軽減した参考になります。
「5つの適正」でサステナブルシフトを考える
しばしばサステナブルという課題には、技術革新による画期的なアプローチが注目を集めます。ただし、前掲した事例のように視点を変えて、販売方法や在庫削減に取り組むなど身近なところで始められるものもあります。
例えば、「5つの適正」は、商品政策の基本的な考えで、適正な「商品」・「時期」・「数量」・「価格」・「場所」で商品販売の最適化をめざすものです。これにサステナブルの視点を加え再解釈すると以下のようになります。
●適正な商品:長持ちする品質や環境負荷の少ない素材を使用する
●適正な時期:販売予測の精度を上げて売れ残りを削減する
●適正な数量:需要予測を基に適正な在庫管理を行い、余剰在庫を削減する
●適正な価格:環境コストを考慮した価格設定をする
●適正な場所:リサイクルやリペアサービスの拠点を提供する
こうしたビジネスフレームも時代にニーズにそって再利用(リユース)してみると別の気づきが得られます。大きな課題もできることを考えることが大事ですね。
経営相談室 スタッフコンサルタント 大西が担当しました。
(※1)出典:環境省ホームページ(https://www.env.go.jp/policy/sustainable_fashion/)
(※2)出典:「「簡単に捨てない」「むやみに新しい物を買わない」を実現する洋服お直しの取り組み事例」(環境省) (https://www.env.go.jp/policy/sustainable_fashion/goodpractice/case20.pdf)
(※3)出典:「リペアを通じて顧客接点を拡大した新たな価値作りの取組事例」(環境省) (https://www.env.go.jp/policy/sustainable_fashion/goodpractice/case02.pdf)
▼大西 森(おおにし しげる)へのご相談(面談)
(2024年12月25日公開)
この記事に関連する大阪産業創造館のコンテンツ















