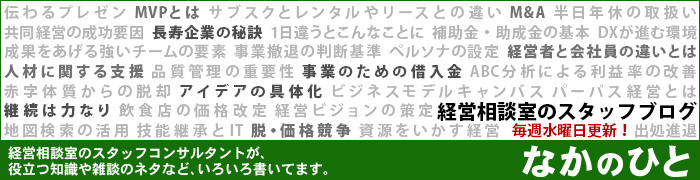
※土日祝除く
FOMOとは?(期間限定の購買心理)
- ハロウィンの経済波及効果
- FOMOとは?
- FOMO活用のポイント
ハロウィンの経済波及効果
明日10月31日は、ハロウィンです。
ハロウィンは今や国民的行事として日本でも大きな季節イベントの一つになっていますが、個人的にはどう楽しめばいいのか、まだよくわかっていません。しかし、経済的な波及効果は大きく、クリスマスに次ぐ経済効果があるとも言われています。この時期はテーマパークからの帰りと思われる“血糊をつけた顔色の悪い人”や“魔法学校のローブを着た人”と電車に乗り合わせるのが普通になりました。

季節限定をうまく活用しましょう
もともとハロウィンはテーマパーク中心で始められ徐々に広まり、SNSの普及に伴い、ネット経由で都市部に人が集まって、大規模なイベントに成長しました。その一例が渋谷のハロウィンです。過度な混雑による影響が問題視され、渋谷では規制が導入されることになりましたが、多くの人が興味を持ってハロウィンに参加していたことが分かる事象です。
ここまで大きくなった背景には、10月の商業イベントが日本では少なかったことや、もともとコスプレ文化もあったので馴染みやすかったことがあります。
今回はこうしたハロウィンなど季節性イベントで使われているFOMOというプロモーション手法についてご紹介いたします。
FOMOとは?
FOMOは「Fear of Missing Out」の頭文字をとったもので、「取り残される恐怖」を意味します。特定の機会やイベントに参加できない、限定商品を手に入れられないことに対する焦燥感を刺激し、消費者の購買心理に働きかけるプロモーション手法です。タイムセールなどは典型的な期間限定プロモーションですが、焦燥感や疎外感などのネガティブな人間心理にアプローチするものを指しています。ハロウィンでは短期間に限定されていることに加え、仮装など見た目が怖いビジュアルもあり、大きな効果が期待できるプロモーション手法として採用されています。
例えば、大手コーヒーチェーン店では季節ごとに限定のドリンクを販売しており、この戦略にFOMOを活用しています。私がここ数か月確認しただけでも、数週間ごとに新しいメニューが登場し、限定感を強調することで、顧客の来店を促進しています。さらにハロウィンには普段とは違ったゴシック調のデザインを取り入れ、限定要素を高めた商品ラインナップとインストアプロモーションが展開されています。
FOMOは、人間心理を利用したプロモーション手法です。特に、損失回避の心理に基づき、人は何かを得る喜びよりも、失うことへの恐れに対して強く反応します(プロスペクト理論)。このため、期間限定や数量限定といった条件を提示することで、消費者は『今行動しないと損をする』という欠損感を感じやすくなります。
FOMO活用のポイント
FOMOはプロモーション手法の一つであり、マーケティング戦略全体の一部です。全体的なマーケティング戦略との整合性、ターゲットの興味や欲求に合わせた設計が必要になります。「欠損感」は人によって異なりますので、ターゲットを明確にしてメッセージを検討する必要があります。デメリットとしては、限定メニューを買えなかった残念な感覚は顧客離れの原因になること、限定品の売れ残りは不良在庫になると考えられますので、適切なマーチャンダイジングも求められます。
ハロウィンを季節イベントとして顧客と楽しむだけでも効果はありますが、FOMOを活用することで、季節限定イベントをさらに魅力的に演出することが可能です。限られた時間で強くアピールすることは大きな効果をもたらす反面、逆効果になるリスクもあるため、慎重に活用することが求められます。
時流に合わせたプロモーションを取り入れ、コアなファンと1年に一度のイベントをより楽しめるといいですね。今年はどんなハロウィンになるのか楽しみです。
経営相談室 スタッフコンサルタント 大西が担当しました。
▼大西 森(おおにし しげる)へのご相談(面談)
(2024年10月30日公開)
この記事に関連する大阪産業創造館のコンテンツ















