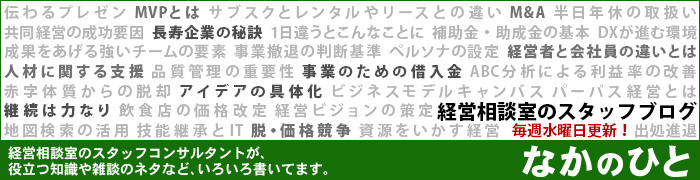
※土日祝除く
未来技術の「社会への定着」を考える
- 顔認証改札機の定着は?
- 新しい技術が日常になるためのポイント
- 多様性時代の設計思想
顔認証改札機の定着は?
地下鉄のOsaka Metroにある「顔認証改札」は全134駅中130駅に設置されています。大阪・関西万博開催に向けて、2023年11月より準備が進み、今年3月から一般向けにサービスが開始されました。

多様性と一貫性でサービスを設計しよう
個人的にアニメやSFみたいで面白そうとは思いつつ、利用をしている人を見たことがなく、使い慣れたICカードが便利なので二の足を踏んでいます。顔認証はパソコンやスマートフォンにも搭載され、流通業の無人化店舗でも一部試験導入が進んでおり、今後、一般的になることが期待される技術ですが、なぜ顔認証改札はあまり利用されていないのでしょう。
今回は大阪・関西万博の開催中ということもありますので、技術の普及を考えてみました。
新しい技術が日常になるためのポイント
便利そうではあるけど普及が進まないものは意外と多くあり、コミュニケーション学者、エベレット・ロジャーズの「イノベーター理論」の5つの顧客層やマーケティングコンサルタントのジェフリー・ムーアの「キャズム理論」(※1)でモデル化されています。
推し活グッズを例にすると、新しいモノ好き(イノベーター)が“痛バ”(※2)に飛びついた後に、情報発信者層(アーリーアダプター)の共感を得て、推し活を楽しむ層(アーリマジョリティー)に広く伝播したことで、今や“痛バ”は推し活には欠かせないアイテムとなりましたが、このように新しいものの普及には段階があります。
キャズム理論では技術が一般化するまでは、“深い溝”が存在し、社会が新しい技術をどう社会に受け入れるかが課題となります。大阪・関西万博で使われる技術(地下鉄の顔認証、NFTなど)は、新しいモノ好きだけでなく、来場する人全員が何らかの形で体験するので技術普及のハードルは低く見られがちですが、一時的な体験に頼っているだけではキャズムは超えられません。特に私たちは、すでに慣れた仕組みを「やめる」ことに大きな心理的負担を感じがちです。だからこそ、技術が社会に普及するには、「便利である」ことだけでなく、「使ってみたい」と感じてもらえる設計や体験そのものが重要になります。
多様性時代の設計思想
顧客とのタッチポイント(接点)は、サービス設計において非常に重要です。大阪・関西万博のように、年齢、国籍、ITリテラシー、身体的条件などが大きく異なる人々が一堂に集まる場では、「一律のサービス」では対応しきれない現実があります。たとえば、駅の改札を通るだけでも、顔認証、ICカード、クレジットカード、二次元コードなど、求められる手段は多様になります。
そのような中で経営判断に求められるのは、自社のリソースの範囲で「どんな方法で、いかに接点を持つか」という幅を広げながらも、提供する価値のコア(安心・利便性・信頼など)の部分は一貫させることです。大阪・関西万博ではまさに、そうした利用者への多様性への配慮とサービスの一貫性といった設計思想が求められていると感じます。
顔認証改札が今後どこまで定着するかはわかりません。しかし、“誰にとっても使いやすい社会”をどう作るかという視点とサービス設計思想は、レガシー効果(※3)として残る可能性はあります。
マーケティングではターゲットを一つのペルソナに絞ることがよくありますが、こうしたサービス体験の設計現場では、逆にペルソナの“幅”に対応する柔軟性が求められます。利用者ごとに異なる入り口(タッチポイント)を用意しつつも、「届けたい価値」は絞り込む。
大阪・関西万博は、そうした設計思想が可視化され、実際に体験できるまたとない機会です。
とはいえ、私はまだ会場を訪れていません。近々行く予定ですので、まずは難しいことを考えすぎずに、未来社会の片鱗を楽しんでみようと思います。皆さんも、ぜひ楽しんできてください。
経営相談室 スタッフコンサルタント 大西が担当しました。
(※1)キャズム理論:キャズムとは溝(英語:chasm)を意味し、ある製品が世に出た際に、その製品が普及するために超える必要のある溝について説いた理論のこと
(※2)痛バ:痛バックの略で、推しキャラクターやアイドルのグッズ(缶バッジ、キーホルダーなど)を大量に装飾したバッグのこと。
(※3)レガシー効果:ある行動や取り組みが終わった後も長期的に良い影響をもたらす現象。たとえば、1970年の大阪万博は、旅行ブームの火付け役となり、さらに「おしゃれをして出かける」文化(いわゆるアンノン族)を広めたとされており、万博のレガシー効果の一例とされている。
▼大西 森(おおにし しげる)へのご相談(面談)
(2025年6月11日公開)
この記事に関連する大阪産業創造館のコンテンツ















