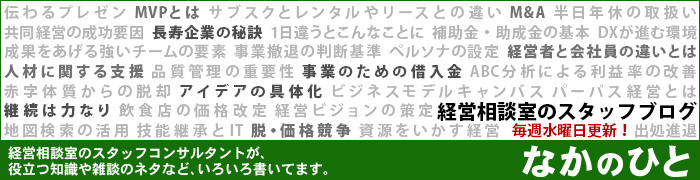
※土日祝除く
経営戦略の本質とは
- 目的達成に向けた方向性
- 環境変化に応じた資源最適化
- 目的を実現するための判断軸
目的達成に向けた方向性
こんにちは。経営相談室の三輪です。

経営戦略の本質理解が成長を導きます!
猛暑が過ぎ、ようやく秋らしい季節となってきました。今年の夏も、熱中症対策や作業環境の整備など、事業活動に直結する課題が浮き彫りとなりました。経営においては、外部環境の変化に応じて戦略的に事業計画を遂行する意識を持ちたいものです。
みなさんは「経営戦略とは?」と問われたら、ひと言でどう答えますか?経営戦略には唯一の定義は存在せず、研究者や実務家によってさまざまな定義が提唱されています。これは、経営戦略は概念であり、多様な捉え方ができることから、結果として、本質的な意味が捉えづらいことが考えられます。
そこで今回、改めて「経営戦略」の本質をご説明します。まず、「経営戦略」の言葉を分解して考えます。「戦略」の語源は「戦場において勝ち残るための知恵と工夫」です。「経営戦略」とは、経営者が置かれている経営環境を戦場に見立て、その厳しい経営環境において経営者が「目的」を実現するための方向性といえます。
環境変化に応じた資源最適化
では、この経営環境をなぜ戦場と見立てるのでしょうか。経営環境とは企業が経営を行う際に置かれている外部環境と内部環境に分けられます。外部環境には、政治・経済・社会・技術といった「マクロ要因」と、競合や取引先、顧客などの「ミクロ要因」があり、これらの外部要因によって経営は大きく左右されます。
一方、内部環境では企業内の経営資源(ヒト、モノ、カネ、情報など)に制約があり、資源配分を戦略的に考えなければ、資源の豊富な企業が優位に立ちます。だからこそ、外部環境の変化と内部資源の制約のなかで、何に集中し、何を捨てるのかという判断が求められます。経営戦略を描き実行することで、厳しい競争環境においても目的を実現することができるのです。
つまり、経営環境の変化に応じて限られた資源を最適化するために経営戦略が必要となるのです。
目的を実現するための判断軸
目的(理念)や目標(ビジョン)を達成するためには「経営課題の設定」が重要となってきます。現状と目的・目標とのギャップが経営課題であり、経営戦略に基づいて施策(戦術)を検討し、戦略との整合性を持たせることで経営者としての判断軸が形成されます。また、経営戦略を実行していくうえでは「経営管理」が不可欠です。戦略を形骸化させないためには、PDCAの仕組みを整え、進捗把握や軌道修正を行うことで戦略を着実に実現して経営管理していきます。加えて、経営戦略そのものは環境変化に応じて柔軟に見直すことも求められます。
近年は「戦略は計画的か創発的か」という議論が注目されています。現状分析を踏まえて戦略を策定し実行する計画的戦略に対し、日々の業務や環境変化への対応から、結果として形成される創発的戦略も重視されてきており、今後のブログで改めて取り上げたいと考えています。
つまり、環境は目まぐるしく変化しますが、組織が目的(理念)を実現するための判断軸はブレてはなりません。経営戦略の本質とは企業目的を実現するための判断軸です。
ここまで経営戦略の本質について整理してきました。この考え方は経営に限らず日常生活にも応用できます。例えば、限られた時間を読書にあてるか、友人との交流にあてるかを選ぶのも、自分の人生の方向性をどこに置くかという判断軸といえるでしょう。経営戦略の本質を理解しそれを実行に移すことこそが、持続的な成長を支える大きな力となります。
経営相談室 スタッフコンサルタント 三輪が担当しました。
▼三輪 華奈(みわ かな)へのご相談(面談)
(2025年10月15日公開)
この記事に関連する大阪産業創造館のコンテンツ















