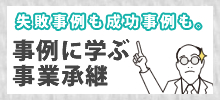ただし、みなさまに問題点をわかりやすく考えていただくため、少し脚色しています。その点はご容赦ください。
第66話「将来を語らない経営者は参謀からも見放される」
創業50年を超えた会社の話です。
創業社長は傘寿(80歳)を過ぎても元気に会社経営の第一線に立っておられました。
そこには、実子は女子ばかり3名で、その配偶者も含め、会社には無関係という背景もありました。
事業承継、次の社長を誰にするかも口にすることなく、傘寿を超えられていました。
そして、突然、社長が逝去する事態が起こってしまいました。
当然ながら次の社長を誰にするかで、創業家は蜂の巣をつついたような状態に陥りました。
社員の中には適任が見当たらず、もしいたとしても高額になっている自社株を取得させることは不可能でした。
家族会議を開いて相談したところ、次女の配偶者が手を挙げました。
ただ、当人は長くファッション関係のデザイナーとして活躍してきており、経営に携わった経験はありませんでした。
しかし、他に手を挙げるものがおらず、同人に経営を託すことになりました。
不安を抱えての船出。
不幸にもその不安は的中してしまいました。
その原因は、新社長の勘違いでした。
業績に不安のない中堅企業であったことに慢心もあったのか、表面的には自由に見えた創業社長と同等であるかのように勘違いした振る舞いが目についたのです。
公私混同と指摘されそうな言動もありました。
加えて、創業社長の逝去に伴い会社の将来を不安に思った幹部数人が会社を去っており、社員の間の動揺は隠せませんでした。
そのような中での社長の行状で、社長と社員の間には深い溝が生まれていきました。
この状態を目の当たりにした創業者の奥様は大変心配し、親しい経営者に相談したところ、大手企業の経営幹部を経験された方を紹介されました。
会って話をしたところ、信頼に足りる人物であると確信し、社長の補佐として力を貸りることにしました。
参謀として迎えられたその方は意気込んで会社に入られたのですが、しばらくしてオーナー家の希望と現実のギャップに気が付かれたのです。
まず、その人事を望んでいなかった社長は、会社の情報を必要以上に伝えようとはしませんでした。
さらに事業の将来性について、社長としての考えがなく、雑務をすることで社長業を行っている気になっている。
それが現実だったのです。
参謀は、社員とのコミュニケーションを密にすることから始め、組織の活性化、総務関連事務の効率化などに取り組みました。
しかし、あまりの溝の大きさに、本来の力を発揮するまでには至りませんでした。
物足りなさを感じられたのでしょう。
招かれてから1年ほどで退職の申し出となってしまいました。
社長の交代時に、新社長の弱点を補う人材を招く会社は多々見られます。
その中で上手くいっている会社の社長には、次のような共通点が見えます。
新社長が、将来に向けてのビジョンを掲げ、取り組んでいこうとする意欲を持っている。
それを補佐役と共有するとともに、社長自身に不足するものを上手く補ってもらおうとする姿勢で臨んでいる。
情報交換を密にし、相互に信頼して将来を共有することが、会社成長の原動力となるのです。
場当たりな経営をされている今回の会社に将来があるのか、不安を感じたのは私だけではないと思います。
(2019年7月23日更新)
担当:田口 光春(タグチ ミツハル)
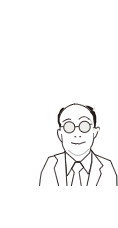
バックナンバー
- 第100話(最終回)「事業承継を知見して思うこと」これまで筆者の40年近くにわたる中小企業との関わりの中で見聞きした事業承継の事例から、100社近くの皆様が興味を持たれる…
- 第99話「創業者をリスペクトした後継者の対応」事業承継についていろいろな相談を受けますが、2つとして同じ内容のものはありません。その中で後継者からの相談で比較的共通し…
- 第98話「信頼した仲間の裏切りにあった承継話」今から20年以上前、創業10年足らずの機械部品の製造会社で起こった事業承継の顛末です。扱っている製品は特段目新しい物では…
- 第97話「脱同族をめざすも悲劇に見舞われた会社の結末は」私がその会社を知った時、創業者はすでに引退しており、故郷の地域おこし支援に転身されていました。信頼のおける役員を社長に指…
- 第96話「会社の存続のためのM&A」ある企業の事業承継対策について紹介します。それは第7、22、27、36、52、58、68話で紹介したM&Aにまつわる話で…
- 第95話「優しい婿養子の悲しい顛末」創業社長にお会いしたのはほぼ半世紀前でした。インテリア家具の製造会社を創業し、業界で注目される会社に育て上げておられました。…
- 第94話「婿への承継は夫婦円満が前提」このブログでは第67話で実の息子ではなくその妻を後継者に指名し成功している事例や、第80話で緻密な後継者教育で娘婿を立派な後継者に育てた事例を紹介するとともに、…
- 第93話「船頭が多いと迷走しやすい事業承継」10年ほど前に出会った会社の話で、「船頭多くして船山に上る」ということわざそのものの事態に遭遇しました。…
- 第92話「会社の状況に適した後継者が見つからない時の策とは?」今回もM&Aにまつわる話ですが、会社の将来を考えた結果、創業家の総意で得た結論で行われた事業承継でした。…
- 第91話「真の会社の姿と、経営者の事業に対する思いが継ぐか否かの判断材料」事業承継の相談を多く受けていて、後継候補者からの相談で数多く寄せられたもの中で代表的な事例を紹介します。…
- 第90話「非同族化した会社の事業承継策」その会社と出会ったのは約25年前でした。既に創業一世紀を超えた名門企業で、売上は3桁億円、従業員は4桁名となっていました…
- 第89話「非同族化には用意周到な準備が必要」今回の事例は、親族での承継ができなかった話です。その会社とめぐり合ったのはほぼ半世紀前。当時は創業者の社長が健在で、まさ…
- 第88話「複数の子どもの処遇の仕方」80歳を超えても会長として息子である後継者をサポートしている会社の事業承継、子どもが複数いる場合における処遇の仕方につい…
- 第87話「オーナー経営を放棄した3代目」事業承継の多くの事例を見てきて思うことは、直系、特に経営者の子息・子女に承継することが一番いい選択であり、殆どの場合で大…
- 第86話「覚悟の決まらない会社売却はうまくいかない」この事例集では多くのM&Aについて紹介してきました。うまくいった事例としては第7話、第22話、第56話がありました。また…
- 第85話「ちょっと待った、その承継対策!」その会社と出会ったのは25年以上前です。既に創業から半世紀以上経過した会社で、当時(現在も)の社長は創業者の子息であり、…
- 第84話「円滑承継の鍵は正直な情報開示」今から10数年前に出会った、一代で世間が注目する食品製造会社を育て上げた社長の事業承継の話です。社長は当時60歳を若干超…
- 第83話「学業優秀な後継者だと期待していたら・・・」かれこれ20年以上前に起きた悲しいお話です。ある精密機器メーカーは祖父の代に創業し、その後父、そして30歳代の働き盛りの…
- 第82話「所有と経営の分離で勘違いした社長」今から30年以上前に出会った会社の話です。当時はオーナーが社長でしたが、複数の会社を手広く展開されており、私が…
- 第81話「先代社長が重宝した幹部は後継者世代でも力になるとは限らず」その会社を知ったのは20数年前です。既に社長は交代されており、30歳代後半の方が社長でした。もちろん面識を持ったのも…
- 第80話「娘婿への社長交代は入念な計画に基づいて」今回は、入念な準備の末に娘婿に社長を譲られた会社の事例をご紹介します。その会社と出会ったのは20年以上前のことです。…
- 第79話「不安の残る事業承継への株式による対策とは?」およそ10数年前のことです。とある会社の社長が私を訪ねてこられました。「70歳に近づいたので、社長を交代することに…
- 第78話「経営者保証は後継者の選択肢を狭める」その2代目社長に出会ったのは四半世紀ほど前になります。父親が創業したインテリア用品の製造メーカーを引き継ぎ…
- 第77話「限られた時間での承継を迫られた社長の決断」今回は、親族が社内にいたにも関わらず、社長の遺言により非同族化した事例です。その会社を知ったのは20数年前になります。…
- 第76話「経営者が後継者の適・不適を決めるものは?」第72話・第73話に続いて女性後継者の事例を取り上げます。社長と知り合ったのは…
- 第75話「所有と経営の分離は難しい?」まもなく創業1世紀を迎えようとする金属製品製造会社の話です。2代目から3代目に経営者が引き継がれたのは、40年近く…
- 第74話「後継者にする基準は?」創業から70年になろうとしている製造業の事例です。私が2代目社長にお会いしたのは、社長就任間もなくの30年ほど前のことです。…
- 第73話「周到な準備を経て娘に承継」典型的な男性の職場と思われる鉄鋼業で、後継社長に娘を抜擢した話です。話を伺ったのは、間もなく同社が創業1世紀を迎えようとしていた時。…
- 第72話「突然の承継を謙虚な姿勢で乗り切った20代の女性後継者」創業1世紀近くになる地場産品メーカーの、20数年前にあった社長の交代にまつわる苦労話です。現社長は3人姉弟の次女、姉と弟がおられました。大学卒業時には…
- 第71話「非同族化にはオーナー家の理解が必要」今から20年ほど前にお会いした社長の話です。ある地方でコンピュータのシステム設計を主業としている会社でした…
- 第70話「父に反発するも選択は後継者」今から20年以上前のことです。とある社長と親しく話をする機会がありました。その内容は社長のこころの叫びのように感じられました。…
- 第69話「株式の力が息子の将来を奪った!?」私がその会社に関わったのはほぼ20年前。3代続く老舗企業でしたが、その事業規模たるや一部上場企業に匹敵するものでした。その礎を築いたのが3代目社長で…
- 第68話「M&Aは『思い立ったが吉日』」今回は、もうすぐ創業一世紀に近づこうとしていた会社のM&Aが絡んだ事業承継の事例をご紹介します。現社長の父親が個人創業で始めた金属部品加工がスタートでした。…
- 第67話「実子よりその嫁を選択した訳は?」昨今は娘が後継者になる事例も多くみられるようになりました。これまで、第32話や第46話でもその一例を取り上げました。今回は息子の配偶者、つまりは嫁が後継者になった話です。…
- 第66話「将来を語らない経営者は参謀からも見放される」創業50年を超えた会社の話です。創業社長は傘寿(80歳)を過ぎても元気に会社経営の第一線に立っておられました。そこには、実子は女子ばかり3名で…
- 第65話「社長ができる後継者兄弟のトラブルの可能性を未然に防ぐ方法」複数の子どもがいる経営者の事業承継の難しさは、本シリーズでも紹介してきました。例えば、後継者指名が混迷した第59話、経営者が苦渋の選択をした…
- 第64話「新しい元号を迎え事業承継を考える」5月1日をもって新元号「令和」になりました。元号が新しくなって、気が引き締まった感を覚えるのは私だけではないと思います。「この機に事業承継、社長の交代を具体的に考えないと」…
- 第63話「中継ぎ社長は所詮中継ぎ」創業80年を迎える電気機器向け金属部品メーカーの話です。約20年ほど前に創業社長が逝去されました。創業社長には子どもが3人、皆さん女性でした。それぞれが良き縁を得て家庭を築き…
- 第62話「兄弟承継から社員承継への方針転換はなぜ起きた?」第42話で兄弟が関わる承継の難しさをご紹介しました。それは後継候補者の資質による問題と、継がせる側の気持ちの問題がある…
- 第61話「兄弟円満に承継・経営していくコツとは?」兄弟平等で事業を引き継ぐことの難しさは多くの企業で散見される事例です。本編でも様々な事例をご紹介してきました。今回は、兄弟仲良く事業に関わり、まもなく創業一世紀を…
- 第60話「叔父と甥の関係は複雑」現在では創業1世紀を超える、合成樹脂成型品の製造会社の承継に関する物語です。会社は元来、木製品製造を生業にして創業しましたが…
- 第59話「親子の情が経営を惑わす」創業から半世紀。大手上場企業の下請けながらも、発注企業が持ち得ていない技術力で確固たる地位を確立している企業で起こったケースをご紹介しましょう。…
- 第58話「M&A(会社売却)を行うには経営者の残りの人生も描く必要あり」日本の中小企業を取り巻く喫緊の問題が“廃業数の増加”であると、官民挙げて問題提起しています。それを解決する手段として大いなる期待をされているのが『M&A』です。…
- 第57話「大政奉還の可能性を残した事業承継対策」創業60年を超える精密機械部品メーカーが行った事業承継について紹介します。私がその会社と接点を持った時の社長は、創業者の三男でした。…
- 第56話「承継の行き詰まりをM&Aで解決」創業半世紀になろうとしていた家庭用日用雑貨の製造卸業で、3代目社長が悲劇に襲われながらも事業承継に立ち向かった会社の話です。…
- 第55話「創業家をリスペクトする会社は強い?」ここ数年、出光興産と昭和シェル石油の合併問題に注目しています。それは出光興産の創業家が合併に反対し、その先行きが全く見えない状況にあったからです。…
- 第54話「『会社の公器化』で非同族化と身内への配慮を果たす」「会社は公器である」と一般的によく使われる言葉ではありますが、非上場の中小企業の場合、必ずしも当てはまる言葉ではありません。反対の表現として、「社長は『かまどの灰まで自分の物』」という…
- 第53話「経営の実権・実績へのしがみつきが時に経営判断を狂わせる」いつまでも社長の椅子や経営実権を離すことができず、その結果厳しい現実を突き付けられた事例はこれまで第2話・第20話・第47話でご紹介してきました。今回もそれらの事例に勝るとも劣らないお話し…
- 第52話「同族で分散した株主構成の会社でもM&Aはできる?」まもなく創業1世紀を迎えようとする食品卸会社の事業承継の事例です。地域で確固たる営業基盤を築き、食品メーカーからも厚い信頼を得ていました。…
- 第51話「事業承継のたびに業種転換した会社」最近、「ベンチャー型事業承継」という言葉が使われ、新たな事業創出の支援策も出てきています。今回ご紹介するのは、既に半世紀以上前から、それも複数回に亘り、新たなチャレンジをしてきた企業…
- 第50話「外部からの社長招聘は難しい」創業70年を超える会社で、私が知り合った当時60歳代後半であった2代目社長に関わる話です。精密機械の重要部品を製造し、業界では高い地位を確保していました。…
- 第49話「外部人材をトップに据え、本命の後継者を教育」創業50年を超える精密機械メーカーの話です。社長は創業者の息子で2代目。既に創業者は他界されており、2代目社長から3代目への事業承継もそろそろといった時期に差し掛かっていました。…
- 第48話「社長の健康状態も経営・承継の重要課題」社長は創業者で、一代で中堅企業に育て上げた実力派社長でした。娘婿が専務として入社しており、後継者として遇していました。社長がまもなく喜寿を迎える年齢となったある日、言動が何か変であることに家族が気づき…
- 第47話「『守破離』で事業転換した後継者」その3代目社長と初めて名刺交換した時、私の発した言葉は、「あれ、社名と事業内容が合いませんがな」でした。「創業時の事業内容を社名につけていたのだけれど、数年前に事業を転換したんだ。でも…
- 第46話「専業主婦が社長に」地方で誕生し、積極的な事業所展開や企業買収を行い、全国的な会社に成長させた創業者の事業承継物語をご紹介します。創業者の強烈なリーダーシップがこの会社の成長の源でした。しかし、その裏側には…
- 第45話「非同族化で事業を引き継ぐ」創業半世紀、大手企業に依存した商売ではありましたが、高い信頼を得て、順調な推移をしていました。将来性は、現状の事業だけでは大きな成長は期待できないものの、安定した業績は間違いない状況と周りも認めるところでした。…
- 第44話「大胆な自社株・相続対策」ニッチ分野ながら特殊な計測機器を開発、販売し、世界的な知名度をもつ会社の話です。その機器の原型を作ったのは先代である創業者で、それを発展させて現在の地位を確立したのが先代の息子3人です。…
- 第43話「宮里藍選手の引退発表に見る事業承継のタイミング」多くの経営者が趣味として愛好するスポーツ、ゴルフの大スター宮里藍選手が2017年5月末に突然に引退を表明しました。アマチュアの高校生がプロトーナメントで初めて優勝するという快挙を遂げた宮里選手。…
- 第42話「やはり創業者は自分の直系に継がせたい?」一代で特殊設備メーカーをトップ企業に育て上げた経営者の話です。社長には女性のお子様が一人。当時は既に学者の元に嫁がれており、お孫さんも二人いました。経営の補佐役として実弟を専務にしていました。その専務には…
- 第41話「思い通りの承継には経営権の裏付けが必要」戦時中、国の指導によって、同じ事業をする会社が強制的に合併させられることがありました。今回ご紹介する企業も、その特異な経緯を経た会社です。元々あった数社の会社のオーナー家がそのまま株主となっているため、当然ながら株式は分散し…
- 第40話「相続は思い通りできるものではない」機械工具卸を創業して40年になろうかという会社の話です。現在の社長が創業し、専務である奥様と夫婦で事業を盛り立て、今では業界で一目置かれる地位を築くに至っています。社長の年齢は還暦をとうに過ぎ、事業承継を真剣に考えなければならない時期に来ていました…
- 第39話「雇われ社長の立場は脆弱」創業2代目から経営を託された非同族社長の悲しい話です。会社は日用雑貨を中国の協力工場で製造し、国内の量販店などに販売しています。創業は第2次世界大戦後まもなくでした。…
- 第38話「経営権=株式保有の裏付けのない経営は危うい」10数年前に出会ったとある社長のご経験です。創業100年になろうかという歴史のあるメーカーを経営されていました。事業もすこぶる順調な様子で、その秘訣や今後の事業の方向性をお聞きすると、楽しそうに披露してくれました。
しかし、話題を変えて事業承継についてお聞きすると、声のトーンが急に落ちてしまいました。… - 第37話「直系後継者をじっくり育てる」一代で海外子会社を複数持ち、売上高100億円の企業に育てた経営者の事業承継の事例です。特に、経営の承継を見事に舵取りした事例でした。創業社長は子どもにも恵まれ、長男を後継者含みで入社させていました。…
- 第36話「M&A後の苦労は誰のせい?」その会社は当時業歴80年ほどを誇り、社長は2代目で創業者の息子が就任していました。そろそろ事業承継、社長交代の時期を迎えていましたが、社長の子どもは女性2人で承継には興味がありませんでした。…
- 第35話「株式対策は会社が儲かっているほど苦労する」 高収益であり、未上場企業は自社株評価が高くなります。 儲かっている企業ゆえの悩みでもあります。…
- 第34話「相続トラブルの泥沼化は誰のせい?」 かなり深刻な事態に陥った会社の話です。
創業者一代で業界大手に登りつめたサービス業を営む会社でした。
社長の幅広い人脈が事業の基盤であり、経営はワンマンで行われていました… - 第33話「M&Aで兄弟それぞれを尊重した事業承継」 大手企業と肩を並べて業界で一定の地位を確立している中堅企業の話です。
創業から間もなく1世紀を迎えようとしており、社長も創業家直系で3代目となっていました。
ある時、同業者からM&Aの申し込み(相手側企業の譲渡希望の話)があり… - 第32話「娘夫婦の見事な承継策」 社長の唯一の悩みは後継者問題。
間もなく喜寿を迎えようとしているのに後継者が決まっていなかったのです。
子どもは女の子が一人、しかもその当時は会社経営とは全く縁のない美術教師でした。
ただ一縷の望みもありました。… - 第31話「用意周到な引退劇」 会社はその社長によって創業され、技術の評価は高く取引先は海外にも広がっていました。。
まさに一代でグローバル企業を育てた立志伝中の人物のひとりと言ってもいいでしょう。。
その社長は向学心も高く、いずれは海外、アメリカでそれまで行ってきた経営を検証してみたいという思いを胸に秘めていました。… - 第30話「老舗ゆえの選択は廃業」 20世紀初頭に創業し、戦後の日本経済の復興・成長とともにあった老舗企業の話です。 同社が扱っていた機械は日本のみならず海外にも名を馳せており、自他とも認めるトップメーカー。
そして迎えたのが時代の大きな潮流、メカニカルからエレクトロニクス、アナログからデジタルへの変化です… - 第29話「セブン&アイに見る未上場企業における事業承継のヒント」 最近の事業経営に関するニュースで、コンビニ業界のトップ企業「セブンイレブン」の持株会社のトップ交代が注目されました。
事の起こりは子会社であるセブンイレブンの社長を交代させようとしたこと… - 第28話「子どもが後継者に適しているとは限らない」 現社長は創業者の孫で3代目にあたります。還暦を迎える数年前に、承継を考えて大手企業で研究職にあったご子息を社内に入れました。
社内の各部門を経験させた後、還暦を迎えたときに社長交代をされました… - 第27話「会社を売却し、社長は新たな道にチャレンジ」 自ら開発した精密機器の部品メーカーとして創業されました。その部品は、日本のみならず全世界で販売されており、業績は順調そのもので、アメリカ、東南アジアに現地法人を持つまでになっていました。経営は順調で社長には悩みがないように思われました。しかし、たった一つ、後継者問題を抱えていたのです。。…
- 第26話「事業承継と社会貢献」 社長は事業承継について真剣に考えなければならない時期を迎えていました。社長のご両親は他界されており、配偶者も子どももいない。となると相続人は兄弟姉妹、もしくはその子どもとなります。この時の社長の相続人は姉妹の子である甥と姪でした。…
- 第25話「夫婦離縁しても実の子どもは後継者候補」 社長は数年前に離婚されていましたが、もうすぐ成人を迎えるご子息が一人ありました。 ご子息は母方で生活しており、最近はほとんど顔を合わせていないとのことでした。…
- 第24話「創業家の『君臨すれども統治せず』の姿勢が会社を発展させる」 中堅大手で経営トップに非同族が就任し、同族脱皮した会社があります。
ただ、やむを得ずなったといった方がいいかもしれませんが。… - 第23話「見事な事業承継には社長の覚悟と寂しさがつきもの?」 社長が実父である先代から社長を譲られたのが38歳の時。
その時、父親に「私のすることは黙って見ていてほしい。相談した時もすべて『Yes』と答えてください。」と社長になる条件を出し、先代もその通りの対応をしてくれたそうです… - 第22話「経営権を手放しても経営の第一線に立ち続けることがある。」 父親から事業を引き継いだ中堅企業の社長の話です。社長には子どもがなく、社長自身も一人っ子で、いわゆる甥、姪といった係累もいなかった…
- 第21話「スズキの社長交代のニュースに接して!」 2015年6月に自動車メーカー「スズキ」の社長交代のニュースが伝わりました。今回はそのニュースをもとにお届けします…
- 第20話「相続税で苦しむのは後継者です」 一代で超優良企業を育て上げた社長の話です。社長の人生は会社そのもの、趣味は仕事、寝ても覚めても考えるのは会社のことばかり…
- 第19話「嫁姑問題が事業承継に影響することも」 ベンチャービジネスという言葉がまだなかった85年ほど前に、大学での研究成果を事業化すべく創業した会社で、創業者の孫が3代目に就任する時に起こった話です…
- 第18話「時間をかけて非同族企業に脱皮」 ある老舗企業の歩んだ道です。社長には事業運営に関して特段悩みはありませんでしたが、唯一、後継者、事業承継が頭の痛い問題でした…
- 第17話「後継予定者に襲った悲劇」 あるメーカーの話です。社長には息子2人と娘1人がおり、長男は商社、次男は電機メーカーに勤め、娘は嫁いでいましたが、後継者選びにはさほど苦労しないと思われていました…
- 第16話「時代に翻弄された事業承継」 いわゆるセレブ御用達で、皇室にも納めていた製品を製造販売していました。社長には実子がおらず、甥を社内に迎え後継者候補にすることにしました…
- 第15話「老舗だからこそ起きたトラブル」 創業3四半世紀を迎えようとしていた企業の話です。株式は創業者の子ども2人(男子と女子)一族に引き継がれ、それぞれほぼ同数を保有、その他重要な取引先にも関係強化のため応分の株式を保有してもらっていました…
- 第14話「時間のない事業承継は選択肢が少ない」 「実は・・・」と始めた話は驚愕の内容。社長は悪性の腫瘍に侵され、既に手の施しようがなく余命1年と宣告されていたのです…
- 第13話「見事な出処進退」 見事な成功を遂げた企業の事例をご紹介しましょう。とある会社に数年ぶりに訪ねてみると…
- 第12話「非同族化は派閥が生まれるリスクも」 「同族脱皮」はとても魅力的、理想的な言葉です。しかし、現実はどうであったか…
- 第11話「冷たい親と思われるかもしれないが」 その会社は創業50年を超え、現在は4代目が社長を務めておられます。その4代目を後継者に決められた経緯…
- 第10話「子どもを平等に扱うと事業承継で問題に」 社長には3人の子ども、2人の男子と1人の女子がいました。親である限り…
- 第9話「究極の事業承継対策は株式上場?」 懇談の締めくくりとして「ところで後継者はどうされるのか?」と質問したところ、「それが・・・
- 第8話「優しい経営者の後に残るものは」 とある老舗の会社の株主総会に出席したとき、ご高齢の株主が多数出席されている状況に驚きを感じました。多数の高齢株主がいることについての話を聞くと…
- 第7話「会社売却で得た安泰な老後生活」 一代でベンチャー企業を育て上げた経営者のお話しです。60歳を超え、そろそろ引退の時期を考え…
- 第6話「創業家以外のものは銀行保証に躊躇する」 業歴100年を超える高収益のメーカーの話です。この会社では、100年間、創業家が代々経営を担ってきました…
- 第5話「どの子どもに継がせるか決めるのは難しい」 複数の子どもを持った経営者によくある悩みの一つが、どの子を後継者にするかです。 とある企業の事例を見ていきましょう。かなりの業歴を誇る企業の話です…
- 第4話「承継は突然に!」 社歴80年を誇る企業の話です。先代社長は3代目ながら、ワンマン経営で事業を大きく伸ばしたように見られる、中興の祖といった経営者でした…
- 第3話「遺言は財産分配を記すだけではありません」 会長の務めも果たし円満な経営者人生を終えられた方はどんなことをしていたか…
- 第2話「出処進退は経営者の肝」 70歳を過ぎ経営者交代の時期を迎えた社長は、長女の夫を社長に指名し、自身は会長に就任しました。 しかし、会長になったものの社長の時と何ら変わらず経営の実権を握り続けましたが…
- 第1話「早すぎる承継対策も考えもの?」 早くから長男を後継者と決め、本人もそのつもりで育ってきました。税理士の指導もあり子どものうちから会社の株式を非課税枠の範囲内で贈与し続けましたが…