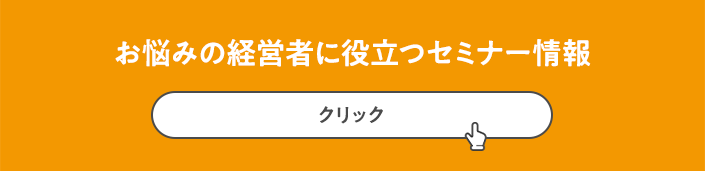人手不足やDX対応が求められる中、小さな会社でも「人が育ち、組織が変わる」リスキリングの取り組みが注目されています。本コラムでは、社員が「言われたことだけをやる状態」だった中小企業が、教育と仕組みづくりによって“考えて動けるチーム”へと変化した実例を紹介。
なぜ今リスキリングが必要なのか、どんな落とし穴があるのか、そして助成金を活用しながらどのように実行すればいいのか──。教育の進め方がわからない、そもそも何を教えるべきか悩んでいるという経営者の方に向けて、実体験に基づく実践的な視点でわかりやすく解説します。
今回は、人材教育やリスキリングの成果を身をもって経験した立場から、「中小企業のリスキリング」についてお話させていただきます。
現在、当社では事業の柱として“人材育成”に本気で取り組んでいますが、私自身、もともとは人材に悩み続けてきた経営者の一人でした。
コロナ禍が明け、世の中が動き出す中で、当社はほぼ止まった状態でした。私一人でほとんどの業務が完結し、社員は「言われたことだけやる」状態。担当間の連携もなく、組織として機能していないことに、日々頭を抱えていました。
その状況は「人を育てる」という意識が自分自身に欠けていたからなのですが、そのことに気づけていませんでした。
そんなとき、ある出会いをきっかけに「リスキリング」や「人材開発支援助成金」という言葉を知り、勉強し始めて、自社でも小さな一歩から教育の仕組みを導入し始めました。
すると、社員一人ひとりに変化が起こり、組織全体が“考えて動けるチーム”へと変わっていきました。
結果として、人材教育によって生産性は大きく向上し、事業の成長にも直結することを強く感じました。
このコラムでは、そうした実体験を踏まえながら、「なぜ中小企業にリスキリングが必要なのか」「その課題と乗り越え方」「具体的な取り組み手順」について、現場目線で解説していきます。
最近よく聞く“リスキリング”って?
Re+Skillで学び直しと勘違いされがちですが、今の仕事に対する学び直しではなく、「これから必要になる新しい仕事のためのスキル」を身につけることを指します。
例えば、営業職からデジタルマーケティング職への転身を目指して新たな知識を習得するように、リスキリングは“仕事の転換”や“変化への対応”を目的とした未来志向の学びです。DXやAI時代の今、企業にも個人にも不可欠な取り組みとなっています。
なぜ今、リスキリングが必要なのか?
人手不足、DX化、顧客行動や取引スタイルの変化など、中小企業を取り巻く環境は日々変化しています。
従業員の教育が後回しになりがちな中小企業にとってリスキリングが必要となる背景には、以下の4つの要因があります。
1. 産業構造の変化が激しい(AI・自動化・DX)
業務のデジタル化やAIの普及により、従来のやり方が通用しない場面が増えています。たとえば、紙ベースで行っていた業務が電子化されたり、アナログ対応だった顧客管理がCRMで一元管理されるなど、“仕組みそのもの”が変わっています。こうした変化に取り残されないためには、社内人材が新しいスキルを習得し、自動化やDXの導入に追随していくことが求められます。
2. 「今ある仕事」が数年後には通用しなくなる可能性がある
野村総合研究所と英オックスフォード大学の共同研究(2015年発表)では、「日本の労働人口の49%が将来的にAIやロボットに代替される可能性がある」と試算されています(出典:NRI『日本の労働市場におけるコンピュータ化の影響』)。つまり、競合企業はテクノロジーを活用して生産性を上げてくる前提で、自社も人員の配置転換や新しい職種への対応が急務なのです。
3. 業界内での“優位性”を維持するには、ノウハウの更新が必要不可欠
ビジネスの常識は、数年で大きく変わります。特にDX、SNS、生成AIなどの新技術は、業界内の競争環境を一変させる力があります。商品力・営業力・サービス品質を高め続けるには、企業としての“ノウハウのバージョンアップ”が欠かせません。社内に新しい知識や視点を取り入れ続けることが、競合との差をつける武器になります。
なぜリスキリングが定着しないのか?──中小企業に潜む“5つの落とし穴”
1.「人材教育=売上」ではないという誤解
2. 教育が事業計画と連動していない
3.「見て覚えろ」という昭和的な職人文化が根強い
4. 経営者の姿勢が社員の学びを左右する
5. 中小企業では教育の“推進役”がいない
中小企業でリスキリングが進まない背景には、根深い5つの課題があります。まず、「人材教育=売上には直結しない」と誤解している経営者が多く、教育投資が後回しにされがちです。また、教育を事業戦略と切り離して考える企業も多く、せっかく学ばせても実務に活かせないまま終わるケースもあります。さらに、未だに“見て覚えろ”“スキルは盗んで覚えろ”という昭和的な指導文化が根強く、属人的な育成から抜け出せない企業も少なくありません。そして、経営者自身が学びや教育に無関心である場合、社員にも「学ぶ意味」が伝わらず、意識が育たないという悪循環に陥ります。大企業と違い、中小企業には人事部や教育専任者がいないことも多いため、教育の推進役は経営者自身が担う必要があります。だからこそ、今こそ「人材育成は経営そのもの」という視点への転換が求められています。
リスキリングはコストじゃない、“逆算で導く投資”です

(図は筆者作成)
企業が売上を上げ、利益を出し、持続的に成長していくためには、まず「生産性の向上」が欠かせません。そして、その生産性を高めるためには、業務の属人化をなくし、誰がやっても一定の成果が出せるようにする「仕組み化」や「業務効率化」が必要です。
さらに、この仕組み化・効率化を本気で実現しようとすれば、AIや自動化ツール、DX(デジタルトランスフォーメーション)といった新たな知識や技術の導入が避けて通れません。これらを自社に取り入れるには、社員一人ひとりが“学び直す”だけでなく、“新しいことを学ぶ”必要があり、まさにリスキリングが重要になってきます。
しかし、ただ「学べ」と言うだけでは機能しません。どの社員に、いつ、何を、どう学ばせるのか――。それを体系的に整理した「教育訓練計画」が不可欠です。そしてその計画は、将来どんな事業に力を入れていくのか、どの分野で勝ち残るのかといった「事業計画」が土台になります。つまり、企業の成長は“事業計画”を起点に、逆算して教育とリスキリングの実行につながっていくのです。
ほとんどの中小企業において、それを実現できるのは社長(経営者)だけです。
つまり、企業の収益や成長を本気で実現したいのであれば、「学ばせる仕組み」を社長自らがつくるしかありません。誰かがやってくれるのを待つのではなく、経営者自身が“学びの旗振り役”になることが、これからの時代の成長戦略です。
事業計画からリスキリング実施までの手順
① 事業計画の明確化
今後3〜5年で「どんな事業を伸ばしたいか」「どの分野に挑戦するか」を明確にする
例:EC強化、DX推進、新サービス開発、業務効率化、自動化 など
② 必要な業務・職種の洗い出し
上記の事業を実現するために、どんな業務や役割が必要かを整理
例:マーケティング担当、データ管理、SNS運用、業務設計、ノーコード開発 など
③ 現在の人材スキルとのギャップ分析
社員のスキル状況を可視化し、「何が足りないか」「誰に何を学ばせるべきか」を見える化
形式:簡単なスキルマップや自己申告+面談など
④ 教育体系の設計(対象・内容・期間・方法)
ギャップに基づき、リスキリング対象者・内容・優先度を決定
教育メニュー例:
AI基礎リテラシー研修(全社員対象)
Webマーケ講座(広報担当対象)
RPA※操作スキル(事務職対象)
※RPA(Robotic Process Automation)とは、人がPC上で行っている定型業務を“ソフトウェアのロボット”に代行させる仕組みのことです。
たとえば、Excelへのデータ入力、請求書の発行、売上レポートの集計、受注内容のシステム登録など、「毎回同じような操作で人手がかかる作業」は、RPAに任せることで自動化が可能です。
⑤ 教育実施の計画と体制構築
外部研修活用/社内勉強会/eラーニング/助成金活用などを組み合わせて、具体的な実施方法を決定
誰がいつ・何を・どう学ぶか、をスケジュールに落とし込む
⑥ リスキリングの実施
計画に基づき、実行(受講→実務反映)
成果を測定できるよう、ビフォー・アフターで簡易的でも効果測定を行う(例:業務改善件数、作業時間削減)
⑦ フィードバックと次の育成計画へ反映
研修や実践の結果を振り返り、次の教育に活かす
教育→実践→改善→再教育というPDCAを回す
DX人材の育成に、国から最大75%の支援 ────人材開発支援助成金の活用
人材開発支援助成金は、企業が従業員に対してスキル習得のための教育訓練を実施した際に、研修費や賃金の一部を助成する制度です。特にDX化に向けたリスキリングを支援する「事業展開等リスキリング支援コース」では、中小企業であれば助成率75%、一人あたり最大30万円まで支給され、企業全体では最大1億円の助成が受けられる可能性もあります。教育の負担を軽減しながら、生産性向上を後押ししてくれる制度です。
リスキリングは、未来の成長をつくる第一歩です。この記事が、あなたの会社でも学びを動かすきっかけになれば幸いです。