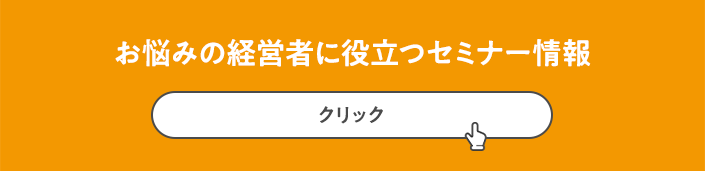掛け売りを行う企業はもれなく、販売代金回収の遅延や不良債権のリスクがついて回ります。債権回収はいくつか手法があり、債務者の出方によって手法を選択し組み合わせていくことが有効です。
今回は債権回収のそれぞれの手法について、その特徴と効果、選択する判断基準について、解説します。
1.債権回収の手法
売掛金債権などの金銭債権は、期限に債務者が支払いをしない場合、債権者が積極的に働きかけて債権を回収する必要があります。期限を過ぎても支払いをしないような債務者は、全部の債権者に対しては、十分な支払いをできない収支・財産状況にあります。したがって、有効な債権回収のためには、自社への支払いを行う優先度を上げておく必要があります。
複数ある債権者のなかで、自社に支払いをしてもらう優先度をあげるには、どのような回収する手法があるかを知って、その事案に応じて手法をうまく組み合わせることが重要です。
手法を大きく種類に分けると、①債務者との協議によって回収していく手法、②裁判所の手続で強制的に回収する手法、③担保を実行し回収する手法の3つに分けることができます。
以下、大まかな各手法の内容と選択する基準について記載します
2.①債務者との協議によって回収していく手法
これは、次の強制執行と対比して任意的な手法と呼ばれています。
この手法は、請求・協議・合意文書等作成・合意内容に沿った支払という流れで進めていくのが基本です。
請求では、文書によって支払の督促を行うのが通常で、これを内容証明郵便で行うことが有効であるとされています。内容証明郵便自体は、送った文書の内容と到達した日時を郵便局が証明してくれるという郵便サービスで、請求を行ったことを証拠化していることがわかる文書です。請求に応じない場合には、裁判等の手段に発展するかもしれないと債務者に予想され、協議に結びつける有効な手法とされています。
請求に対し、債務者が回答や連絡をしてきた場合は、債務者との協議の場面となります。
債務者において、十分な手元資金がない場合、分割支払いなどの条件を提案してくることも多いですが、債務者の金銭以外の財産から回収する手法も検討するべきでしょう。
債権者の側も買掛金がある場合、売掛金と相殺をして買掛金の支払いをしないことで代金を回収することができます。また、債務者が持っている第三者への売掛金債権を債権譲渡してもらったり、委任状をもらい代金の代理受領をすることで第三者から回収することができます。
在庫商品があるときは、本来の債務の支払いに代えて、その商品で代物弁済してもらうなど、譲り受けた商品を売却することで回収する方法もあります。
単に、債務者にお金がないからという話で分割合意とするのではなく、金銭以外の財産から回収できるものがないかを協議し、債務者の協力を引き出し、回収することを検討しましょう。
その上で、分割払いを認めなければ回収できないとなれば、支払いの条件や合意内容などを弁済契約書などの文書で定めておくのが必要です。そもそも、債務者は、本来の期限を徒過しているため、分割を認める代わりの条件として、連帯保証人や担保の差し出しを求めたり、支払い条件に違反した場合に強制執行できるように、強制執行認諾文言付公正証書の作成を求めておくのがよいでしょう。
3.②裁判所の手続で強制的に回収する手法
債務者との協議によって支払いをしてもらうことが期待できない場合、債務者の財産に強制執行をして回収していく手法を検討します。
強制執行を行うためは、執行文の付いた債務名義(確定判決、仮執行宣言付判決、仮執行宣言付支払督促、執行証書、和解調書、調停調書など、強制執行により実現される請求権の存在・範囲を表示した公の文書)が必要となります。
確定判決とは、民事訴訟で勝訴判決を得て確定したものです。民事訴訟については、当事者で争いがある場合、原告・被告が主張や立証を繰り返しますので、判決を得るまで一定の期間を要します。(なお、判決が出るまでに財産を第三者に譲渡などするような場合は、仮差押えなどの手続を検討します。)
裁判上の和解調書や、民事調停での調停調書も、確定判決と同様に債務名義となります。
仮執行宣言付支払督促とは、申し立てにより書記官が債務者に支払督促状を送達し、異議の申し立てがなければ、支払督促に仮執行宣言を付するものです。異議がある場合は民事訴訟に移行しますが、異議がなければ比較的短期間に強制執行手続に移ることが可能です。執行証書とは、2で記載した強制執行認諾文言付の公正証書のことです。いずれかの手段で、債務名義を取得しておく必要があります。
強制執行は、不動産に対する強制執行(不動産の差押え後に裁判所の競売手続により売却し、売却代金から回収)、動産に対する強制執行(執行官が動産を差押え、換価し、配当を受けることにより回収)、債権に対する強制執行(債権差押命令の債務者への送達後、原則1週間の経過による取立てによる回収)の方法に分けることができます。対象の財産を特定して申し立てる必要があります。
近時の民事執行法の改正で、金銭債権の債務名義を有している場合、申立日の6か月以上前に終了したものを除いた強制執行の配当等の手続において完全な弁済を受けられないときや、強制執行を実施しても完全な弁済を得られないことを疎明したときは、裁判所を通じて、預貯金等について金融機関から情報を取得できる制度ができています。また、財産開示の手続を経た場合は、債権者の選択する地域の債務者の不動産について登記所から情報を取得できるようになっています。
これらの新設された制度を利用し、債務者の財産の把握ができれば、把握した財産に対する強制執行の申し立てを行うことが可能となります。
4.③担保の実行により回収する方法
担保の対象となる債務の支払いを怠ったときは、担保を実行することにより、優先的な弁済を受けることができるため、担保は債権回収の有効な手段となります。中小企業が当初から抵当権等の担保を設定することは難しいですが、当初の期限を徒過し、分割支払を求めてくる場面では、交換条件としての担保を求めておくのがよいところです。
不動産に抵当権、根抵当権の設定を受けた場合は、担保不動産競売を申し立てることにより、裁判所に納付された競売代金からの回収が可能です。また、収益物件に抵当権、根抵当権の設定を受けた場合は、家賃などから回収する担保不動産収益執行の申し立ても可能です。
動産について、譲渡担保の設定を受けているときは、担保の目的物を引き上げて、換価処分することが可能となり、処分代金から回収できることになります。
また、主たる債務者にかわって債務を連帯して支払う連帯保証人は、人的担保と呼ばれ、債務者以外に連帯保証人の財産からも回収が図れる点で、債権回収に有効な手段となります。
連帯保証人からの回収をできるよう、分割払の交渉の際には、連帯保証人の提供を条件に入れるべきでしょう
5.まとめ
以上、債権回収の各手法の内容と選択する基準について解説しました。債権回収に王道はなく、地道に複数の手段を組み合わせて粘り強く回収していくこととなります。日ごろの与信管理を怠らず、早めに対応をしていくことが重要です。
大阪産業創造館では、債権や契約に関する内容など、企業法務に強い弁護士が無料で毎日相談に対応しております。
法律に関してお困りのことがあれば、お一人で問題を抱え込まず、まずは気軽にご相談ください。
無料法律相談受付窓口
(※対象は大阪市内の中小企業様のみとなります、その他「面談のご注意」をご確認のうえお申し込みください。)