 |
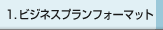
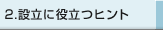
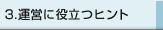
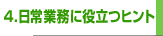
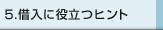
|
 |
 |
 |
 |
第2節 証書の作り方
第1項 証書の綴じ方
証書が何頁かに亘る場合は、その左、又は上、もしくは左上端をホッチキスで留める。
第2項 署名の仕方
最後に契約当事者が署名する。個人の場合は個人名を記載して署名し、法人の場合は法人名と署名する人の名と資格を記載して署名を行う。Aの代理人としてBが署名する場合には、on behalf of AとしてBが署名する。 立会人(witness)と明示して署名した人は、別段の合意のない限り契約内容について権利義務を有することはない。
第3項 訂正の仕方
訂正を要する場合には、その頁を全部タイプで打ち直した方がよいのであるが、時間が無くそのようにすることができない場合は、訂正すべき部分だけ訂正し、その部分の左端の空欄にすべての当事者が署名(イニシアル)する。
第4項 収入印紙
国によっては、その国で作成された契約書について一定の収入印紙(stamp)を貼用することを義務づけている。通常はその国で完成された証書についてのみ適用があり、必要な収入印紙を貼らなければ脱税になるが、契約の効力には関係がないのが普通である。日木の印紙税法によれば契約の最終の署名が日本で行われる場合には、その契約書は日本で作成されるものとみなされて、日本の印紙税法に定めるところに従って印紙税を納めなければならないが、契約書にまず日本で署名を行い、それを外国に送って相手方に署名させることにより契約書を完成するような場合には、日本の印紙税法は適用されず、日本の印紙を貼用する必要はない。
第5項 公証
公証人(notary public)の制度は国によって異なるが、署名が本人のものに間違いないことの認証(authentication)を行うことを公証という。日本で作成された証書を外国に提出する場合、特に相手が官公庁の場合にはその国の大使館や領事館の査証を要求されることもあるが、その場合にはまず日本の公証人に署名が本人のものに間違いないことを認証してもらい、更にその公証人の所属する法務局と外務省の証明を得て、最後にその国の大使館や領事館に行って証明してもらうことになる。
|
|
 |
|
 |